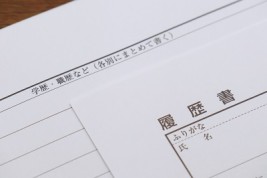Fintechにおいて重要な4つの先端IT技術と求人需要
世界はもちろん、日本でも注目を集めるFintech(フィンテック)。今回の記事では、外国人ITエンジニアの転職エージェント GTalnetが、Fintech(フィンテック)に関連する4つの先端IT技術と各技術に対する求人需要をまとめました。Fintech(フィンテック)において重要な4つの先端IT技術今回の記事ではFintech(フィンテック)において、以下の重要な4つの先端IT技術について取り上げたいと思いいます。AI・ビッグデータブロックチェーンIoT生体認証それでは、各技術に関して現在の求人需要も踏まえて1つ1つ説明していきたいと思います。AI・ビッグデータ株価の情報、経済指数、個人の金融情報などの大量なデータを利用し、クレジットカードや融資の与信審査などにビッグデータの技術が応用されている事例が多く挙げられます。ビッグデータが処理可能なクラウドサーバーや分散処理システム等によりデータ分析のコストが大幅に低下、データの収集や変換もテキストマイニング技術や自然言語処理技術などを用いることで、大量のデータを収集・処理できるようになっています。そして、2010年前後に開発されたディープラーニング技術によりAIの性能が飛躍的に向上し、ビッグデータを使って自動的に金融指標の分析や株の売買、窓口業務の自動化など金融業界の様々な領域でAIの活用が始まっています。それに伴い、銀行等では人がやっていた業務がAIに取って代わられると言われており、各銀行で大きなリストが今後始まっていくと言われており、IT企業に変化できない銀行は淘汰されると言われています。AI・ビッグデータの求人需要実際、大手保険会社やクレジットカード会社などでデータエンジニアやデータサイエンティストなどの求人が増加してきており、ビッグデータを有効活用することで、各社ともに業務効率化や新サービスの創造を図っています。また各銀行においてもITエンジニアの採用に力を入れており、どの金融企業もフィンテック企業に変化することを視野に入れています。しかし、日本国内ではビッグデータやAI関連の人材は不足しています。日本で仕事をするときは、日本語が必要とされるケースが多いですが、一部の日系保険会社では日本語不要で採用をしたりもしており、外国人のITエンジニアが活躍できるフィールドが多くあります。ブロックチェーンフィンテックの技術として一番最初に思い浮かぶ言葉が「ブロックチェーン」と言っても過言ではないでしょう。より専門的な用語で表現すると、「分散型台帳技術」とも呼ばれています。中央集権型の管理ではなく、世界中にあるコンピューターにデータを分散させ、破壊・改ざんなどのリスクが低くなるように作られたネットワークシステムとなります。通常、銀行にお金を預けた場合、取引の記録は銀行の中央サーバーによって管理されますが、ブロックチェーン技術を使えば、金融機関などの中央管理を必要とせず、取引情報をネットワーク上に分散して保存ができるようになります。また、暗号化技術により利用者は許可された項目しか参照できず、個人情報の流出リスクも非常に少ないです。すべての記録はコンピューターのネットワーク上に保存されているため、誰でも精査・監査ができて、不特定多数の人の目にさらされることで偽造や二重払いを防止しています。ブロックチェーン技術が用いられている代表的なものは、ビットコインなどの仮想通貨となります。ブロックチェーンと言うと、仮想通貨をイメージされる方が多い状況ですが、これほどブロックチェーンが注目されるのは、仮想通貨以外の幅広い領域に応用ができ、これまでのビジネスが大きく変革されることが期待されているためです。例えば、通常の商取引、電子投票、契約書の締結など、ビジネスに必要な基本業務においてブロックチェーンが活用されることが期待されています。ブロックチェーン技術の求人需要ブロックチェーン技術が求められる求人は日本においても増加し続けています。仮想通貨事業者だけではなく、銀行などの金融業界、ブロックチェーンのソリューションを提供するスタートアップなど、非常に高い需要があります。また、日本はブロックチェーン技術を持ったエンジニアが少なく、外国人のエンジニアが多く活躍している領域でもあります。IoT現時点では金融領域でIoTが導入されている事例は少ない状況です。しかし、最近では自動車にIoT技術の搭載が進むにつれて、自動車の運転方法のデータと自動車保険がリンクされる可能性が挙げられたり、自動運転が進んだ時の自動車保険の在り方などが議論を読んでおり、金融領域におけるIoT技術が少しずつ注目を集めています。また、医療現場でIoT技術が使われることで、医療保険においても大きな影響を与える可能性があります。最近では、ウェアラブルデバイスの浸透により、Apple Watchの決済対応などもIoT技術が応用されており、今後金融領域におけるIoT技術は成長が見込まれる可能性があります。IoT技術の求人需要IoT技術の市場規模は2020年に36兆円超に達する(Gartner推計)と言われており、IoT技術の需要は今後も非常に成長性が高い分野と言えます。既存の金融会社やフィンテック企業においてIoT技術者の需要はまだ少ない状況ですが、金融会社にリンクされるIoT搭載デバイス(車、ウェアラブルデバイスなど)を製造している製造業におけるIoT技術者の需要は高い状況です。生体認証銀行や証券などオンラインでサービスを利用する場合は、必ず本人認証が一番最初に鍵を握ります。2012年7月には、生体認証を含むオンライン認証を中心とした世界的な認証の標準化を目指すFIDO(Fast IDentity Online) Allianceが、Pay Pal、Lenovo等6社により発足し、現在もその規模を拡大しています。主要企業であるボードメンバーには、Visa、MasterCard、Bank of Americaなどの世界的金融大手に加え、Microsoft、Google、 NTTドコモ等の世界的企業も加盟しています。また、日本の一部の銀行のATMにおいても、指紋や静脈による認証も開始されています。最近では、画像データのみならず、キーボードの打鍵方法等身体運動による認証も開発されており、新しい技術の応用が目覚ましい分野と言えるでしょう。生体認証技術の求人需要生体認証技術に関しては、まだまだ用途が本人認証に限られることもあり、AIやビッグデータ、ブロックチェーンの技術に比べると、需要はまだまだこれからと言えるでしょう。まとめ今回ご紹介した4つ以外にも、フィンテックの分野では様々な新しい先端IT技術が用いられていくでしょう。また、先端IT技術だけではなく、消費者のユーザビリティを上げるためにモダンなフレームワークなども最近では必要となってきています。外国人ITエンジニアの転職エージェント GTalnetでは、今後もフィンテックの動向を随時調査し、必要となる関連技術をアップデートしていきたいと思います。